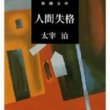文豪・ドストエフスキーというと、『罪と罰』『白痴』『カラマーゾフの兄弟』など、長編小説のイメージが強いかもしれませんが、それらの大作の前にドストエフスキーは『地下室の手記』という中編小説を書いています。
『罪と罰』なども衝撃的でしたが、私はこの『地下室の手記』が特に印象に残っています。私がもともと長い小説よりも短い小説の方が好きというのもあると思うのですが、『地下室の手記』はそれほどの長さがないからこそなのか、人間社会への諦念、絶望とでもいうべき毒の濃度が高まっている感があります。
以下で『地下室の手記』を読んで私が魅力的に感じた点をご紹介しようと思います。
『地下室の手記』の主人公
主人公は40歳の男性。
本人いわく、「病的」で「意地悪」、そして「人好きのしない」人間。
手記を書く前年までは役所に勤めていたが、遠い親戚が多額の遺産をのこしてくれたため、現在は町はずれにある家に引きこもって暮らしている。
「第一 地下の世界」
『地下室の手記』は二部構成になっています(第一が「地下の世界」、第二が「べた雪の連想から」)。
前半の「地下の世界」では、男が自分を病的な人間であると思っていることや、そこから派生して考えていることなどが書かれています。
「地下生活者」=現代日本でいう所の「陰キャ」?
諸君、誓っていうが、あまり意識しすぎるということは、それは病気なのである。
ドストエフスキー『地下室の手記』
いわゆる直情径行の人とか、活動家などが生活の資としているような、あの程度の意識があったら、十分なのである。
ドストエフスキー『地下室の手記』
意識の過剰どころか、どんな種類の意識でも、意識はすべて病気なのである。
ドストエフスキー『地下室の手記』
「意識は全て病気」――軽い、重いの違いはあれど、人間はみな病んでいるということでしょうか?
その中でも、主人公は自分が意識過剰だと思っており、自分とは違い意識過剰でない人を「直情径行の人」「活動家」などと呼んでいます。
主人公によれば、「直情径行の人・活動家」は馬鹿で愚鈍で浅薄らしいのですが、そう悪いことばかりでもなく、彼らは「ノーマル」であり、「自然がかくあれかしと望んだような人間」であるので、主人公は彼らが羨ましいのだそうです。
しかし強烈な意識を有する主人公はどうしても彼らとは相容れないので、羨ましいといいつつも彼らの仲間入りはしたくないのだとか(そしてちょっと小馬鹿にしている)。う~ん、こじらせていますね……。
そして自分のように「強烈な意識を有する人間」のことを、「われわれのように考えてばかりいて、したがってなんにもしない人間」といっています。主人公はこのような人間の生活を「地下生活」とたとえていますが、この地下生活を必ずしも最上のものと考えている訳ではありません。しかし自分が渇望している世界は発見できない……恐らく、現実世界では叶わない? 理想郷なので、
諸君、とどのつまり、なんにもしないのが一番いいのだ!
ドストエフスキー『地下室の手記』
現実世界では「地下生活」が一番ましな生き方、ということなのではないかと(このあたりについては主人公本人にも迷いがあるようで、うやむやになっています。理想郷云々は私の憶測)。
現代日本の用語でいうなら、
- 「直情径行の人・活動家」=陽キャ
- 「地下生活者」=陰キャ
といった所でしょうか。
ちなみに、題名を直訳すると『地下生活者の手記』となるそうで、主人公は地下室で暮らしている訳ではありません(青空文庫では『地下生活者の手記』の題名になっています)。
「二二が四」に憤る
わたしにはなぜかこの法則や二二が四が気にいらないのに、自然律だの数学だのに、なんの係わりがあるというのだ?
ドストエフスキー『地下室の手記』
ただ二二が四だけ幅を利かすようになったら、もう自分の意志も何もないじゃないか? 二の二乗は、わたしの意志なんかなくたって、やっぱり四になるんだからな。自分の意志となると、そんなものじゃありゃしないんだ!
ドストエフスキー『地下室の手記』
二二が四が立派なものだということには、わたしも異存がないけれど、しかしいっそ何もかも賞めることにするなら、二二が五も時によると、愛嬌のあるしろ物なのだ。
ドストエフスキー『地下室の手記』
主人公はこのように「二二が四」に憤っています。
「第一 地下の世界」には「自然の法則」という語句が頻繁に登場するのですが、「二二が四」とはその「自然の法則」の象徴なのだと思われます。
自然の法則とは、掛け算や、石の壁は額で壊せない(屈強な空手家などなら壊せるのかもしれませんが……)というような「あらかじめそういうもの」と決まっている法則のことかと。
しかし主人公は、そういったものは自分が決めたものではないのに、どうしてだかそれに従わなければならないということが気に食わないのではないでしょうか。
諸君はこう叫ぶだろう(もし、諸君がわたしなどに声をかける値打ちがあると認めるならば)、だれもきみの意志を奪おうというものはありゃしない、ただなんとかしてきみの意志がみずから進んで、きみのノーマルな利益や、自然の法則や、算術などと合致するように、うまく仕組みたいと心配しているだけだ、と。
ドストエフスキー『地下室の手記』
何も考えずに「自然の法則」に従えるのが、主人公がいう所の「直情径行の人・活動家」なのだと思います(上でも書きましたが、主人公によると彼らは「ノーマル」であり、「自然がかくあれかしと望んだような人間」)。
「直情径行の人・活動家」は、主人公を見て、「自然の法則に何をそんなに憤っているのだろう? おとなしく従えばいいではないか」と感じ、主人公は彼らを見て、「何も考えずそれらに盲目的に従うのは、自分の意志をないがしろにするようで納得いかない」と感じるのかと。
恐らく主人公も掛け算や石の壁を壊せないという物理的な法則に抗えないことは重々承知しているのですが、人間が決めた常識や慣習などに関しては時には「二二が五」だっていいのではないか、という思いを抱いているのではないでしょうか。
みんなが同じように考え、同じように行動することが望まれるのなら、それは人間ではなくロボットのようなものではないかと――。
犯罪者を無理やり矯正する『時計じかけのオレンジ』のテーマと相通ずるものがある気がします。
生まれつき犯罪者の気質を持った者を、社会に適合するように「作り変える」のは是か非か――。
それはその人の個性を奪うということではないのか……しかし犯罪者が野放しになっていては一般市民としては気が気ではないし……難しい問題です。
「第二 べた雪の連想から」
「第一 地下の世界」では主に主人公の内面世界について書かれていましたが、「第二 べた雪の連想から」では、主人公の過去の行動がいくつか書かれています。それも、思い出すと枕に顔を埋めて足をバタバタさせてしまう感じの黒歴史的な行動です。
2年がかりの小さな復讐
ある夜、主人公が安料理屋の玉突き台の傍に立っていた所、ひとりの将校に無言でどかされます。主人公が通り道をふさいでいたからなのですが、そのどかし方が主人公には「道具のような」「蠅のような」扱いを受けたように感じられた――という訳で、主人公は将校への復讐を企てます。
その復讐方法とは、将校に道でぶつかるというもの。読んでいる身としては、「なんだ、そんなことか」――と拍子抜けする復讐ですが、主人公はびびってしまいどうしても将校にぶつかることができません(将校は堂々と歩いている――しかも大男。主人公は小男)。
しかし主人公はついに目をつぶることによりその小さな小さな復讐を遂げることに成功します。将校にどかされたあの夜から2年後のことです。2年……! よくいえば粘り強い、悪くいえば執念深い主人公の性格が表現されているエピソードです。
誘われていない元同級生の集まりに無理やり参加する
主人公が数少ない友人宅を訪れると、先客がありました。2人の元同級生――彼らは主人公の登場を気にも留めずに、転勤する友人ズヴェルコフの送別宴の話をしています。
主人公はズヴェルコフを憎んでいました。その理由はいろいろあるようですが、結局はズヴェルコフが「直情径行の人・活動家」だからだろうと思われます。
で、主人公は誘われてもいないのに、自らその憎んでいるズヴェルコフの送別宴に参加すると言い出します。
翌日、断った方がいいと思いつつ、主人公はなけなしのお金を握りしめて送別宴が行われるレストランに出向きます。
するとどうしたことか、約束の5時になっても誰も現れない……ボーイに聞くと、送別宴の時間は6時に変更されたとのこと。
6時に元同級生たちが現れますが、悪びれもせずに「(主人公に)時間変更の通知をするのを忘れちゃった」といいます。
もともとズヴェルコフが嫌いなこと、お金がないこと、元同級生たちが平然と遅れてきたこと、そして彼らの自分への軽い嘲笑などにより主人公はイライラし、またお酒が入ったこともあって、食事の場で空気を悪くする発言を連発します。
元同級生たちは呆れて、主人公を置いて娼家に向かおうとします。そこで帰ればいいのに、主人公は友人にお金を借りてまで元同級生たちに付いていきます。
娼婦をネチネチといたぶる
娼家に着いたらズヴェルコフを殴ってやろうと息巻いていた主人公(別々の馬車に乗っていた)。しかし娼家に着くとズヴェルコフの姿は既に見当たりませんでした。そこでまた帰るチャンスがあったというのに、主人公はリーザという娼婦を気に入り一戦交えることにします。
そして約2時間後、
いまとつぜん自分の淫蕩が、まるで蜘蛛のように愚かしく、いまわしいものに思われて来た。
ドストエフスキー『地下室の手記』
――からなのかなんなのか、主人公はリーザを言葉で攻撃しだします。
「お前も今は若いが、いつか最下層の淫売窟に落ちてそこで病気になって死ぬだろう」などといやなことをいってネチネチとリーザをいたぶります。
リーザはまだ二十歳、そこまで暗い未来を思い描いていなかったのでしょうか、主人公のお説教を聞いて泣き出してしまいます。
主人公はリーザに自分の住所を渡して慌てて退散します。
その後リーザは主人公の家にやってくるのですが、主人公は自分の家の貧乏具合や、下男のアポロンと給金のことでもめている所を見られたことから動転し、泣いたり喚いたりお金を渡したりと醜態をさらします。
二十歳の女の子にこのような情緒不安定なおじさんが手に負えるはずもなく……。リーザは主人公の家を後にします。
あとがき
意識過剰であまのじゃくな主人公は、他人との関係をうまく築くことができません。
他人を許せない心の狭さ、そんな狭量な自分を嫌悪して、次第に自分のことも許せなくなる。なので人と関わるのがつらくなるばかり――。そして最終的には引きこもりになることを選びます。
自分を陰キャだと思う人は、主人公に共感できる部分が少なからずあるかもしれません。
ご興味がわいた方は是非お読みになってみてください。