以前、「探偵小説を擁護すべきだったのだろうか」という記事で、探偵小説は純文学より低俗なものとされていた――というようなことについて少し触れたのだが、今回は探偵小説家同士の論争について。
当時(大正~昭和初期)は「純文学 VS 探偵小説」なんてことは恐らく話題にも上らなかったのだろう。それくらい「純文学の方が探偵小説よりも格上」という図式が当たり前のことだったのではあるまいか。純文学作家は探偵小説家を鼻にも引っ掛けていなかったと思われる。
で探偵小説家たちは、大衆からはなかなかの人気を得ていたものの、文学的には何となく程度の低いものとされていて、そのため肩寄せ合って団結していた……かというとそうでもなく、なんと探偵小説家同士で諍いを起こしていたようなのである。
人が寄り集まるとトラブルが発生しやすい、というのは時代を問わず普遍的なことなんでしょうかね……。
探偵小説の定義
まず「本格探偵小説」というものがある。乱歩の探偵小説の定義によると、
探偵小説とは、主として犯罪に関する難解な秘密が、論理的に、徐々に解かれて行く経路の面白さを主眼とする文学である。
江戸川乱歩『幻影城――探偵小説の定義と類別』
とのこと。
日本で探偵小説が書き始められてからしばらくすると、謎解きよりも犯人の心理であるとか、犯罪にまつわるおどろおどろしい雰囲気だとかに主眼を置く探偵小説が現れて、これに「不健全派」(平林初之輔が命名)や、「変格探偵小説」(甲賀三郎が命名)という呼び名がつけられた。
乱歩はこの呼び名に大変抵抗があったようで、後年『人間椅子』『鏡地獄』は怪奇小説、『押絵と旅する男』『パノラマ島奇談(綺譚表記の時もある)』などは幻想小説、『虫』などは犯罪小説と呼んでもらいたい、といっている。
参考文献
「探偵小説の定義と類別」と「探偵小説純文学論を評す」の項。
トラブルメーカー(?)・甲賀三郎
甲賀三郎は探偵小説が流行りだした初期の頃から活動していた本格探偵小説家で、自分がセオリー通りに動機やトリックを考えているのに、「探偵趣味的」とでもいうべき変格探偵小説がチヤホヤされるのが面白くなかったのかもしれない。
『探偵小説百科a』によると、昭和6年、甲賀三郎が『探偵小説はこれからだ』という文を書き、これが論争の口火になったようである。
その中で甲賀三郎は、「探偵小説は小説の形式を借りた謎である」と述べたのだとか。ここでいっぺんに述べたのかどうかはわからないけれど、それだから「探偵小説は文学ではない」とか、「謎解きに無関係な登場人物の性格描写なんか不要である」などとも主張したそうである。
そして大下宇陀児(おおしたうだる)の小説『魔人』を「乱歩の模倣」だと批難したらしい。自分の意見を表明するだけに留めておいたらいいのに、人にケチをつけるとはひと言多いというか……。
で、大下宇陀児もそれに応戦して、「探偵小説の型を破れ。探偵小説が単に謎解きだけであってよいだろうか。従来がそうであったからといって、これからもそうでなければならぬという理由はない」という文を書いたのだとか。
しかし2人はもともと同じ勤務先(農商務省の窒素研究所)に勤めていた同僚だったとのことなので、仲が悪かった訳ではない……のだと思う(それは本人たちしか知る由もないことだけれど……)。
参考文献
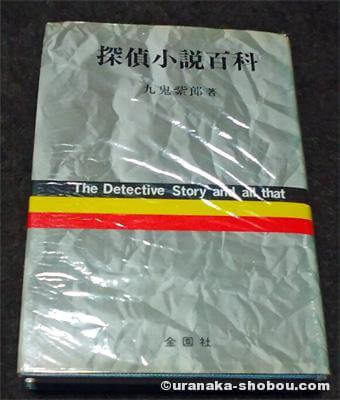
探偵小説百科
「探偵小説論争」と「大下宇陀児」の項。
当時の主だった本格推進派、変格推進派、中立の探偵小説家
| 本格派 | 甲賀三郎、浜尾四郎 |
|---|---|
| 変格派 | 大下宇陀児、海野十三 |
| 中 立 | 江戸川乱歩 |
浜尾四郎について
『君らの魂を悪魔に売りつけよ―新青年傑作選a』というアンソロジーに、浜尾四郎の作品『彼が殺したか』が収録されている。読んだはずなのに全く記憶に残っていない。
浜尾四郎については、私の中では作品よりも責め絵師・伊藤晴雨をだました人という印象が強い。浜尾四郎は突然伊藤晴雨をどこかに連れていこうとした。「僕がついていれば大丈夫だから」という浜尾四郎の言葉を信じて伊藤晴雨がついていくと、そこは裁判所の検事局だった。そして晴雨はそのまま警視庁⇒巣鴨刑務所に10日ほど送られてしまったらしい(艶本を刊行したため)。
団鬼六『伊藤晴雨物語a』には浜本という名で登場している。伊藤晴雨『美人乱舞』にははっきり実名で載っている。「少なくも私は浜尾君を友人として交際して来た(p.138)」という晴雨、かわいそうである。
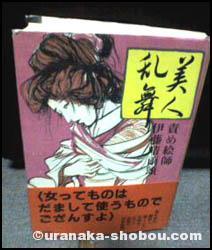
美人乱舞
事件に関しての記述が2回出てきます。「浜尾四郎に呼び出された」(p.138)、「浜尾四郎が晴雨宅を来訪した」(p.153)という微妙な違いがありますが、流れとしては大体上記のような感じです。
元検事で、その頃は弁護士であったという浜尾四郎は、一体どういう心持ちで友人を裁判所に連れていったのだろう。表面では友人ヅラをしながら、伊藤晴雨が描く責め絵を変格探偵小説と同じく撲滅した方がいいと内心では思っていたということなのだろうか。
ところで『彼が殺したか』を読み返してみた所、これがなかなか面白かった。乱歩の『D坂の殺人』を彷彿とさせる性的倒錯が絡んでくる殺人事件の話であった。しかしこれは浜尾四郎自身が推進する本格探偵小説とはいいがたいのでは……。
ちなみにアンソロジーのタイトルである「君らの魂を悪魔に売りつけよ」はこの『彼が殺したか』の一文だった(それについてもスッカリ失念していた私……)。なかなかイカした一文である。
変格推進派の探偵小説家と中立の乱歩について
大下宇陀児
この頃の変格推進派代表? である大下宇陀児も探偵小説初期から活躍していた作家のひとりである。
馬に角を生やそうというような文学的装飾は不要
江戸川乱歩『探偵小説四十年(下)――昭和三十一年度 探偵小説論争』
という甲賀三郎の主張に対し、大下宇陀児は、
角のある馬が役に立つとしたら、馬に角を生やす研究も面白い
九鬼紫郎『探偵小説百科――探偵小説論争』
と返したという(馬の角論争)。
私は大下宇陀児の全作品を網羅した訳ではないけれど、『死の倒影』『蛞蝓綺譚』(『爬虫館事件―新青年傑作選a』所収)などが面白かった。
特に『死の倒影』はグロテスクな絵ばかりを描くという画家が主人公なのだが、その画家は戦慄、狂気、圧迫、そういったものに不可思議な美を感じるという。絵画界の変格派の物語のように読める所が興味深い。
『死の倒影』が収録されている『恐怖特急』というアンソロジー。
海野十三
雑誌『新青年』上で甲賀三郎の本格説に異議を唱えたという海野十三(『探偵小説百科a――探偵小説論争』)。
海野十三の作品では私は『振動魔』『俘囚』『爬虫館事件』『三人の双生児』などが好きである。トリックや殺害方法に理化学的な要素がある作品が多いが、それがしばしば奇想天外な使われ方をするので驚かされる。作品の残忍性・怪奇色も強めで、人でなしな登場人物が多い(気がする)のも印象的。
『生きている腸』のオチなどは訳が分からなすぎてもはやギャグ。
小酒井不木(は私の単なる想像ですが……)
ちなみに、『恋愛曲線』『人工心臓』『痴人の復讐』『メデューサの首』などの著者である小酒井不木が昭和4年に亡くなっていなければ、恐らく変格推進派の一人になっていただろうという気がする。
探偵小説家かつ医学博士でもあった小酒井不木。その作品の多くに医学の知識が活用されている。
乱歩は中立
乱歩の立場はどっちつかずで、「探偵小説にありながらにして、文学的なものが書けたらいいな」――といった感じであろうか。煮え切らないといえば煮え切らないが、バランスがとれたもっともな意見ともいえて、乱歩の常識人ぶりをうかがわせる(作品はぶっ飛んでいるのに……)。
夢野久作が巻き込まれる
昭和6年に甲賀三郎が上記のようなことをグズグズいいだして、その後も浜尾四郎がグズグズいったりしたらしく、チョコチョコした諍いは他にもあったのかもしれない。
昭和6年からその後数年のチョコチョコ具合は私には分かりかねるのだけれど、昭和10年にちょっと驚くべきこと? が起こっている。遅ればせながらという感じで、夢野久作がこの論争に巻き込まれているのだった(ちなみにこの年には『ドグラ・マグラ』が出版されている)。
夢野久作は『探偵小説の真使命』(『文芸通信』という雑誌に掲載)という文章で、鶏や林檎が純粋種から進化して、その時代時代の趣味文化を象徴し、代表しつつ、次第次第に複雑極端になっていった、と述べ、次に、
純粋種は実に尊い、有難いものである。吾吾は純粋種の味を時々回想してみる必要がある。
しかし正直のところ今となっては純粋種はあまり美しいものでも美味いものでもない。
夢野久作『探偵小説の真使命』
鶏の人類に対する真実の使命はその変種にある。食用鶏は卵が少なく、採卵養鶏は肉が美味くない。それでいいのだ。
同様に探偵小説の真使命は、その変格に在る。謎々もトリックも、名探偵も名犯人も不必要なら捨ててよろしい。神秘、怪奇、冒険、変態心理等々々の何でもよろしい。
夢野久作『探偵小説の真使命』
新人よ、躊躇する事は絶対にない。
日本民族の趣味は確実に、敏速に低下して行きつつ在る。
夢野久作『探偵小説の真使命』
こんなことを書いている。
するとそれを目ざとく見つけた甲賀三郎が、別雑誌(『ぷろふいる』)に『夢野久作君に問う』という文章をすかさず書いたらしい。
そこで今度は夢野久作が同雑誌に『甲賀三郎氏に答う』を書いている。
これは『探偵小説の真使命』を甲賀三郎に向けて書いた訳ではないので、返答にちょっと困る……というような書き出しで始まっている。そして大体において『探偵小説の真使命』と同じようなことが書いてある。
ただ1つ大きな違いといえば、前者では夢野久作は「探偵小説が文芸であるかどうかは責任を負う限りではない」と述べているが、後者では「小説と名乗る以上はどこまでも文芸でなければならぬ」としている。これは甲賀三郎の主張とは正反対であるので、挑戦的といえば挑戦的である。
とはいえ、「在来の文芸上の約束に拘泥する必要は一つもない」と足している。この辺は新人作家やその卵たちが気後れしないようにと配慮してのことであろうか。夢野久作の優しさを感じる。
『夢野久作全集7a』では、これに続いて『探偵小説漫想』という短い文章が載っている。これの発表年数や雑誌は不明であるが、書かれたのは恐らく昭和10年だと思われる。夢野久作は昭和11年3月に亡くなっているからだ。
『探偵小説漫想』で、夢野久作は本格探偵小説について、
私は本格探偵小説が書けないけれど、読むのは好きである。でも読者を弄ぶ探偵小説は嫌いだ。紙芝居式の謎々小説よ。呪われて在れ。
と書いている。これまたずいぶん過激な書き方である。甲賀三郎が喜んで噛みついてきそうなものであるが、これについて甲賀三郎が何か述べたのかどうかは分からない。噛みつこうとしたらそれより先に夢野久作が亡くなってしまい、この件はこれでお終いになった――という可能性が高そうである。
参考文献
余談:夢野久作のデビュー当時の話
またまたちょっとビックリな事実があって、話は前後して夢野久作のデビュー当時のこと。夢野久作デビュー作『あやかしの鼓』は新青年創作募集で二等になり陽の目を見たそうなのだが、これを第一に推したのは意外にも甲賀三郎だったらしい。怪奇小説の領分に入っているのが不満だとしつつも、大体の点においては褒めている。
そしてもっと意外なのが、逆に乱歩は『あやかしの鼓』を全く評価していなかったことである。「人物が一人も書けていない」や、「少しも準備がない、出たとこ勝負」などといってケチョンケチョンにこきおろしている。
しかし長所として「全体に漲っているキチガイめいた味」を挙げている。これを感じとっていて、乱歩がなぜ他の点についていろいろケチをつけたのだか私には理解できない。夢野久作はきっと乱歩が好きだったはずなので、これには少なからずショックを受けたのではなかろうか。
参考文献
その後の探偵小説の論争
甲賀三郎 VS 木々高太郎
探偵小説の論争はこれで終わりかというと、実はここからが本番で、昭和11年、甲賀三郎が木々高太郎の小説『就眠儀式』を批難し(……)、それに応戦する形で木々高太郎が「探偵小説も芸術でなくてはならない」と主張した(探偵小説芸術論)。
これにまたまたナニを、とばかりに甲賀三郎がグズグズ文句をたれたのだそうだ(『探偵小説百科a――木々高太郎』)。
いちいち絡みにいく甲賀三郎も甲賀三郎だが、応じた木々高太郎の主張もまたかなり極端である。
一般的には「探偵小説芸術論争」というとこの2人のやりとりが有名らしい。甲賀三郎は相変わらず謎解き謎解きで、木々高太郎は人間を描くべきだとか、これまでの変格論者よりもっとご大層なことを主張したらしい。
木々高太郎はドストエフスキーの『罪と罰R』なんかも探偵小説の範疇に入り、今後探偵小説家はああいったものを書くべきだというようなことをのたまったのだとか。それだと純文学と探偵小説との違いは一体何なのかと乱歩なんかは戸惑ったようである。
デビュー1、2年目のひよっこのいうことなんだから、10年ほど先輩である甲賀三郎は大目に見てやればいいのに……と私なんかは思ってしまうのだが、木々高太郎がその年直木賞なんか獲っちゃったもんだから、甲賀三郎は「これ以上でかい顔をされてたまるか」という脅威を木々に感じていたのかもしれない(それかただ単に現代でいう所の老害的存在……?)。
私は木々高太郎の小説もそんなに読んでおらず、『睡り人形』くらいしか覚えていないのだが、これはなかなかに変態的でショッキングな作品であった。
『睡り人形』が収録されているアンソロジー。乱歩の『人でなしの恋』でも感じたが、余計なことを話したり余計な動きをしたりしない人形のような女性(や人形そのもの)に惹かれる男性は割と多いのかもしれない。しかも現代ではその数が昔よりも増えていそうな気がする。
木々高太郎の直木賞受賞作である『人生の阿呆』は夢野久作の『氷の涯』に少し似た趣があるという噂。しかし『氷の涯』ほどインターナショナルな雰囲気ではないらしい。
『氷の涯』といえばそのスケールの大きさも魅力だとは思うが、私としてはニーナという意志の強い女主人公と、あの美しく、壮大で切ないラストシーンが何といってもツボなので、ああいった感じであれば今後読んでみたいと思う。
江戸川乱歩 VS 木々高太郎
戦後にも、今度は乱歩が本格派代表といった感じで木々高太郎と論戦したらしいのだが(甲賀三郎は昭和20年没)、これは『ロック』という雑誌の売上を期待してのことだったらしい。
木々君の文学論と、私の本格論との論争は、「ロック」という雑誌ではじめたのだが、あれには編集長の山崎君が論争の形で呼びもの記事を作ろうとして、私達に勧めたのに対して、多少八百長的に応じた嫌いがないでもなかった。
江戸川乱歩『探偵小説四十年(下)――昭和二十五年度 抜討座談会』
加えて乱歩はもともと中立の立場であるのだから、それほど議論にも熱が入らなかったのだろう。恐らく「甲賀 VS 木々」のような盛り上がり方はしなかったと思われる。
また読者側にも変化があった可能性がある。もしかすると、探偵小説の熱心な読者がもうそれほどいなくなっていた時期だったのかもしれない。だからこそプロレス的に「乱歩 VS 木々」の論争を仕掛けたりする必要があったのかもしれない。
参考文献
「昭和二十五年度 抜討座談会」の項。「昭和三十一年度 探偵小説論争」の項では、「馬の角論争」からそれまでの探偵小説論争をざっと振り返っている。
あとがき
でまァ結局、私が思ったことといえば、夢野久作はやっぱりいいこというな……というのと、自分は自分、他人は他人、と自分がやりたいことをやっていればいいのに、他人が自分と違うことをやっていると「何だか気に喰わない」と口出ししてくる輩がいるということ。イヤなものを無理に褒めることはないけれど、自分と違うからといって、他人に自分の意見ややり方を押しつけてくるような人はちょっと困る。
現代ではそういう困った人はごくごく少数だと思うのだけれど、全くいない訳ではなさそうなので、もしそういう困った人に出くわしてしまった時にどう対処するかを日頃から少し考えておいてもいいかもしれない(まァ相手にしないのが1番よさそうですかね……)――ということを、前置きの記事とあわせてお伝えしたかった記事でした。
tag おすすめ記事, 伊藤晴雨, 夢野久作, 小説, 江戸川乱歩




















































